10月20日の1年生の「総合的な探究の時間」授業では、静岡県企画部統計活用課主事小野佑月様による「分析考察の統計学入門」と、静岡県立中央図書館長髙橋健二様による「プレゼンスキル入門」の講座を同時開催しました。同じチームのメンバーが別々の講座を聴講することにより、異なる知識やスキルの情報を共有し合い、今後の探究活動を発展させていきます。
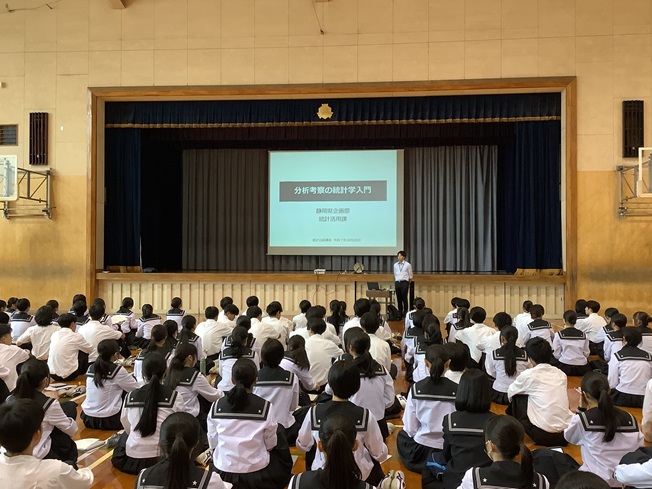
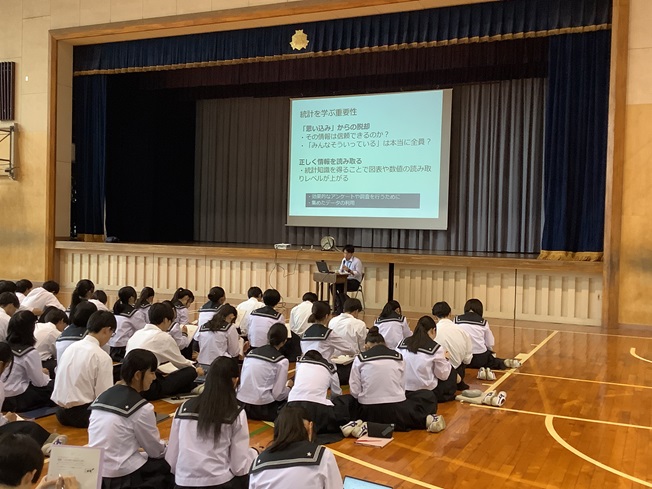
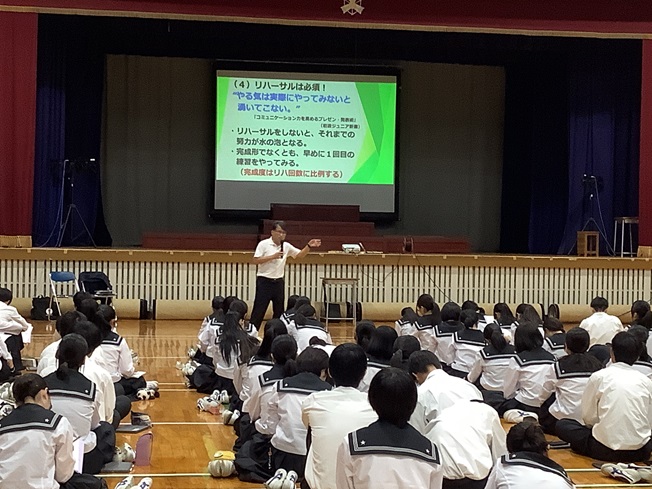
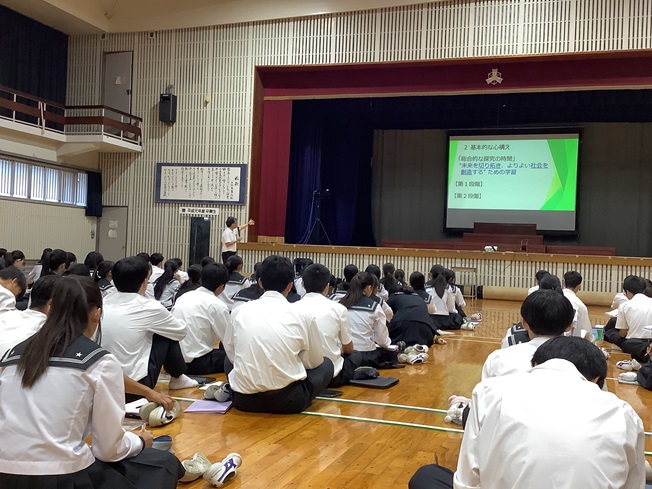
生徒の感想
- 統計学のデータは、普通に読み取るより、深掘りをする読み取り方をすることによって、その調査での本質のようなものが見えたり、この調査って本当に正しいのかなというような疑問が生まれてきたりするということがわかったので、今後ネットや自分たちで作成したデータは注意しながら読み取りたいです。質問の仕方のお話では、質問する側の重要な観点だけではなく、質問される側の気持ちやアンケートや質問の答えやすさなども意識する必要があることを学びました。統計学はこれからの活動の大切なヒントになってくるので、しっかり学んだことを理解し、活用していきたいです。
- 分析・考察のための統計学入門の講話を受けてみて、自分が調べたことや考えたことを表すのに、統計を使うととてもわかりやすいということがわかりました。また、統計を取ったり、使ったりする上では様々な注意点があるということを知り、思い込みや誘導することができるような方法は正しい情報を表すことができなくなってしまうため、気をつけていきたいと思いました。このような様々な注意点に気をつけながら統計などの数字を使っていきたいと思います。
- わたしは今まで、事前調査の質と量がプレゼンの成功につながると思っていましたが、先生の講話を聞き、事前調査で得た結果をより有効的に聴衆の皆さんに伝えるためには、スルーラインとストーリーの構造をよく理解し、本当に伝えたいことを強調するスキルが大切だと考えました。 わたしたちの班ではまだまだスルーラインがはっきりしていませんが、これからプレゼンの構造を考えていく中で、先生のお話を参考にさせていただきながら、自分たちのスルーラインを見つけていきたいと思います。
- 授業やフィールドワークといった探究活動は「自分のため」の活動で、プレゼン発表は「自分のため」に調べた情報をいかに相手に伝わるようにするかが重要と思った。自分の「伝えた」という事実と、相手に「伝わった」という二つがどちらもあってこそ、次の活動に臨むことができると考えた。また、相手に「伝わる」ようにする工夫の中で、相手の立場と主題とのかかわりを明確にすることで、ストーリーもより没頭して聞いてもらうことができ、スルーラインも意識してもらえると思った。探究活動とプレゼン発表の目的をしっかりと理解し、意識を変えて発表作りをしていきたい。

